発達障害(はったつしょうがい)とは、生まれつき脳の発達に特性があり、コミュニケーションや行動、学習などに困難が生じる障害の総称です。主に3つの種類があります。
主な発達障害の種類
- 自閉スペクトラム症(ASD)
- 対人関係やコミュニケーションの困難
- 興味や行動が限定的でこだわりが強い
- 感覚の過敏・鈍麻(音や光に敏感など)
- 注意欠如・多動症(ADHD)
- 注意が続かず、忘れ物やミスが多い(不注意)
- 落ち着きがなく、じっとしていられない(多動)
- 衝動的に行動してしまう(衝動性)
- 学習障害(LD)
- 読む(読字障害:ディスレクシア)
- 書く(書字障害:ディスグラフィア)
- 計算する(算数障害:ディスカリキュリア)
など、特定の分野の学習に困難がある
発達障害の特徴と対応
- ひとりひとり特性が異なり、得意・不得意がある
- 適切な支援や環境調整(例:視覚的なスケジュール管理、静かな環境の確保)が大切
- 早期発見と理解が、本人の生きやすさにつながる
発達障害は「個性の一つ」とも考えられ、適切なサポートを受けることで能力を活かしながら生活することができます。児童福祉の分野でも、発達障害の子どもへの支援がとても重要です。
発達障害と法律
発達障害は、**2005年に施行された「発達障害者支援法」**によって、正式に法律で定義されました。
この法律の目的は、発達障害のある人が適切な支援を受けられるようにすること。対象には、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)などが含まれます。
その後、2016年の改正で、支援の対象が乳幼児から高齢者まで広がり、学校や職場でのサポートも強化されました。
この法律によって、発達障害への理解が深まり、より生きやすい社会を目指した取り組みが進められています。
我が家の次男は、5歳の時に自閉症スペクトラム障害・重度の知的障害と診断されました。
自治体や主治医に相談し、支援を受けることができています。
別な記事で詳細をお伝えしますね。

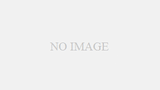
コメント